みなさんは犬も脳梗塞を起こすということをご存知でしょうか。
脳梗塞は脳の血管が詰まって脳細胞が壊死してしまう病気で、人間の場合は発症してすぐに亡くなってしまったり、後遺症が残ってしまったりすることもあります。
では、犬が脳梗塞を起こしてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。
そこで今回は犬の脳梗塞について、症状や寿命、復活・回復する可能性などを詳しくご紹介していきたいと思います。
▼この記事に書いてること
いざというときに落ち着いて対応できるよう、しっかり覚えておきましょう。
犬の脳梗塞の症状とは
犬が脳梗塞を起こした場合、症状は梗塞が発生した場所によって異なります。
| 梗塞場所 | 症状 |
|---|---|
| 大脳 |
|
| 小脳 |
|
一般的にはこれらの症状が突発的に現れます。また、梗塞が軽度であれば無症状のこともあります。
犬の脳梗塞には前兆がある?
人間の脳梗塞の場合は、片手がしびれて物を持てなくなってしまったり、ろれつが回らなくなったりといった前兆が現れますが、犬の場合前兆はほとんどないといわれています。
というのも、仮に人間と同じような前兆があったとしても、犬の場合は言葉を発することができず、私達飼い主に体の異常を訴えることができないからです。
そのため、日頃から愛犬の様子をよく観察して、少しでも早く症状に気づいて治療を受けさせてあげることが重要です。
目の様子が変?
犬が脳梗塞を起こすと、目が回っているような状態になります。そのため、眼球が意志とは関係なく一定方向に往復運動をする「眼振」という症状が現れます。
眼振があるからといって必ずしも病気とは限らず、頭を強く振ったり車などに乗ったりするときにも生理的な眼振が起こることがあります。
しかし、何もしていないのに眼振が起こっている場合は、脳梗塞に限らず、脳などになにかしらの異常が発生しているサインです。
そのため、愛犬の目が上下や左右に一定のリズムで動いている場合には、すぐに動物病院を受診するようにしましょう。
寝たきりになる?
犬が脳梗塞を起こすと平衡感覚がおかしくなったり手足が震えたりするので、寝たきりの時間が増えます。
脳梗塞は高齢犬で発症することが多いため、寝たきりの時間が増えても老化現象の一つととらえられ、見過ごされてしまうこともあるかもしれません。
しかし、起き上がった後にまっすぐ歩くことができない、斜頸や眼振がある場合などは、脳梗塞を起こしている可能性が考えられます。
寝たきりの時間が増えたな、と感じたら、脳梗塞の症状がないかどうかしっかり愛犬の様子を観察し、何か異常があればすぐに動物病院を受診しましょう。
痙攣を起こす?
犬の脳梗塞で見られる痙攣は、基本的に片側性に起こります。
また、手足に痙攣が起こるとうまく歩けずふらついたり、片足を引きずったりすることもあります。
水を飲まない?
犬が脳梗塞を起こすと、水を飲まないというよりも、うまく歩けなかったり頭を上げられなかったりして、水を飲みたくても飲めないことがよくあります。
ただし、水を欲している場合は口元に水を運んであげれば飲んでくれます。
そのため、あまり水を飲んでいないな、と感じたら、シリンジやスポイトで直接口の中に水を入れてあげたり、水飲み用のお皿を持ってきて頭や体を支えてあげたりすると良いでしょう。
犬の脳梗塞の寿命は?
人間が脳梗塞を起こすと寿命は5年以上縮むといわれていますが、犬の場合は今のところはっきりとした寿命はわかっていません。
しかし、梗塞を起こした場所や治療を始めるタイミング、基礎疾患の有無などによって、犬の脳梗塞の寿命は大きく異なります。
また、梗塞が起こっている部位が大きかったり、心臓病や腫瘍などの基礎疾患が原因で脳梗塞が起こっていたりする場合は、予後が悪いといわれています。
犬が脳梗塞から復活・回復する可能性は?
必ずというわけではありませんが、犬が脳梗塞を起こしても早期に発見してすぐに治療を開始することができれば、2〜3週間で症状が改善し、復活・回復するといわれています。
ただし、場合によっては四肢が麻痺して寝たきりになってしまったり発作が起きたりと、後遺症が残ってしまうケースもあります。
リハビリすれば治るの?
脳梗塞の後遺症が治るかどうかは、脳が損傷を受けた程度などによって異なります。
つまり、リハビリをして治ることもあれば、一生お付き合いをしなければならないこともあります。
犬のリハビリの内容は、人間とほぼ同じです。
| 運動療法 | プールやバランスボールを使った運動 |
|---|---|
| 徒手療法 | マッサージやストレッチなど |
| 物理療法 | レーザー療法や温熱療法など |
犬用のリハビリプールは限られた施設にしかないため、事前に自宅付近にプールを使ったリハビリを行っている動物病院や施設があるかどうか確認しておくと安心でしょう。
▼リハビリ用プールを使ってリハビリを行っている様子です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
犬の脳梗塞は前兆がほとんどないため、気がついたときにはかなり時間が経っていて、一命をとりとめても後遺症が残ってしまうことがあります。
そのため、愛犬の異常にいち早く気づき、すぐに動物病院を受診することが大切です。
犬の脳梗塞は稀な病気ではありますが、こちらの記事を参考に、今から心得ておきましょう。
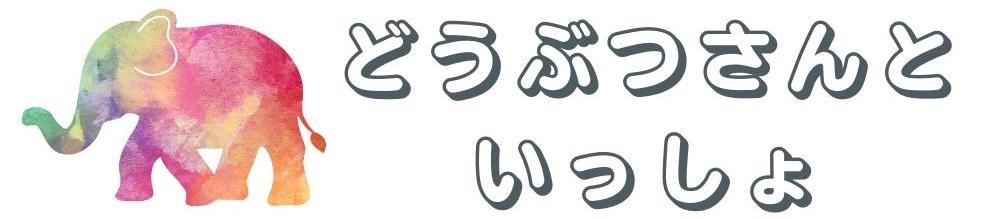


















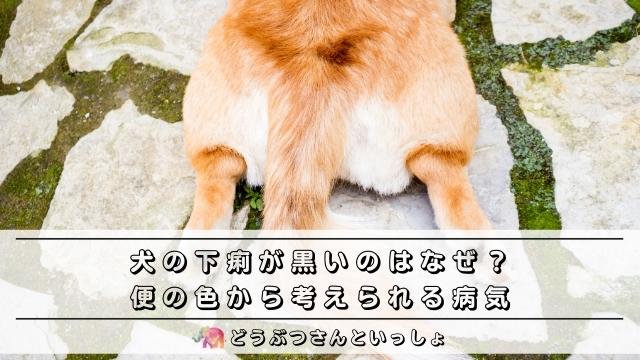



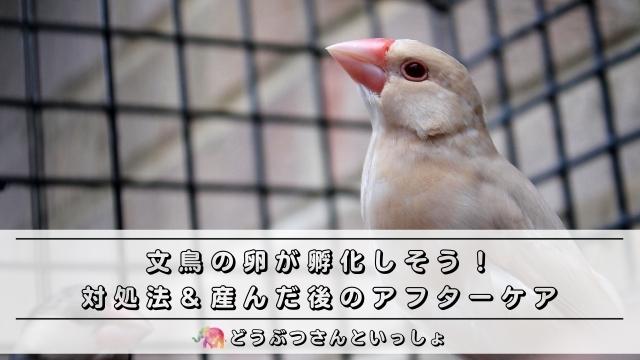
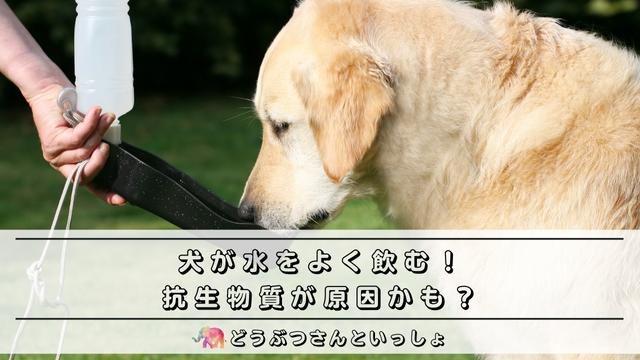
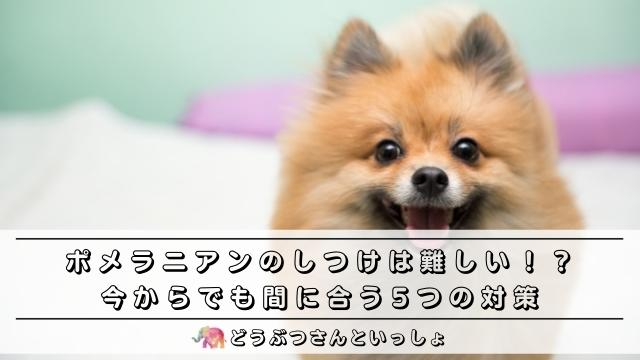



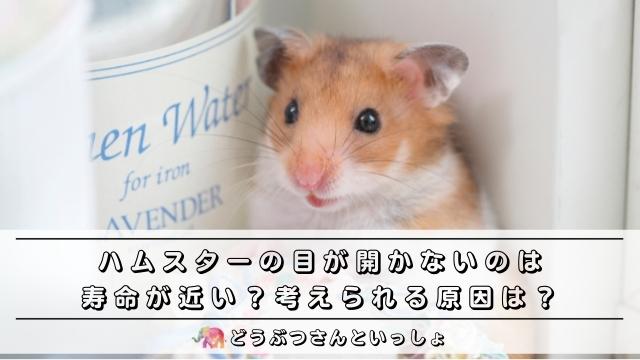
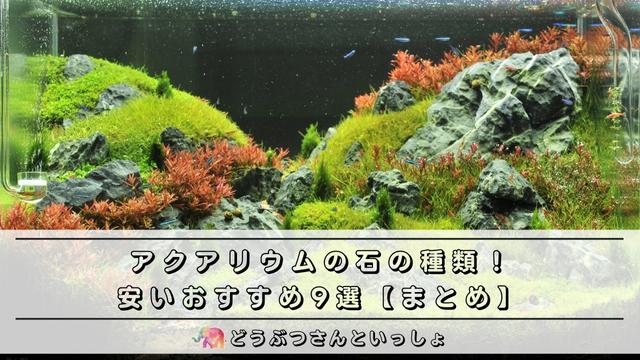

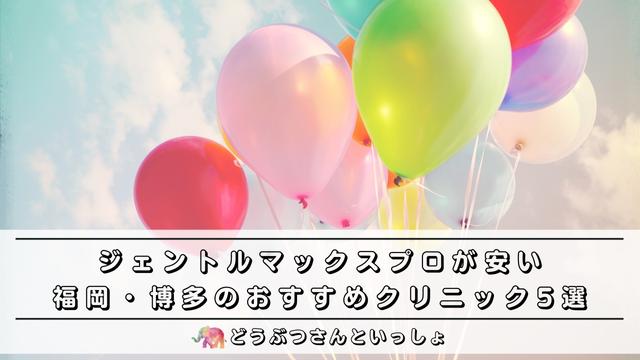


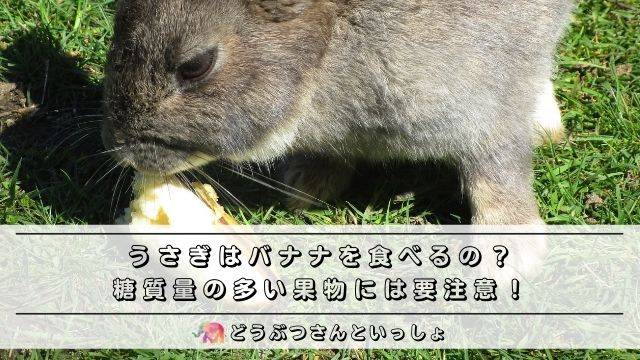



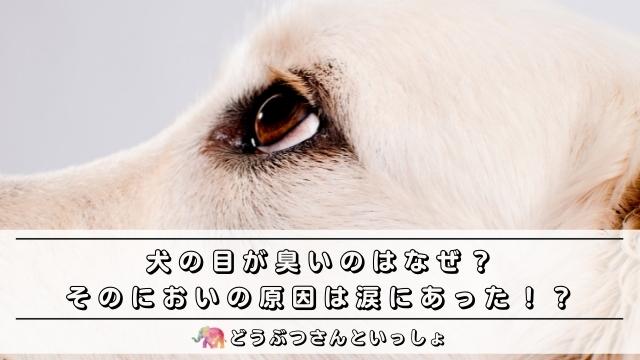
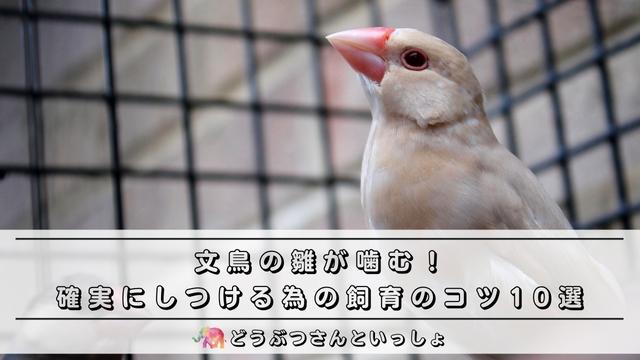

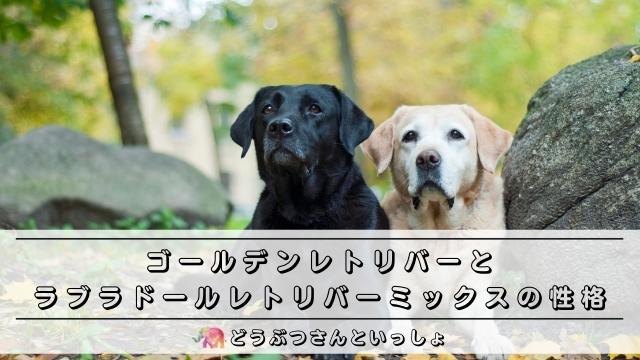
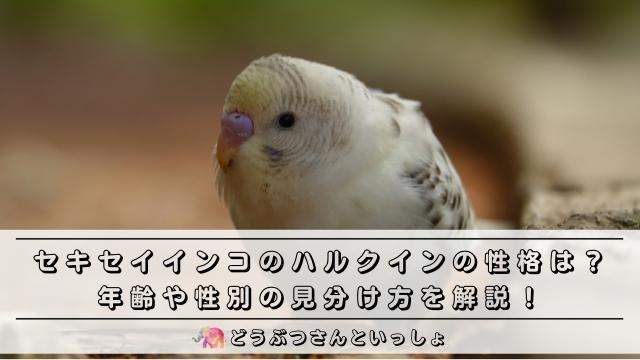
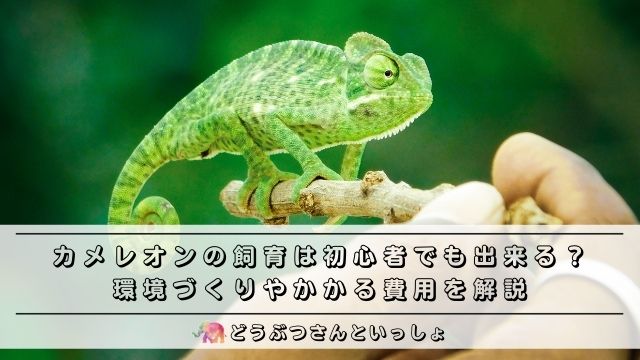
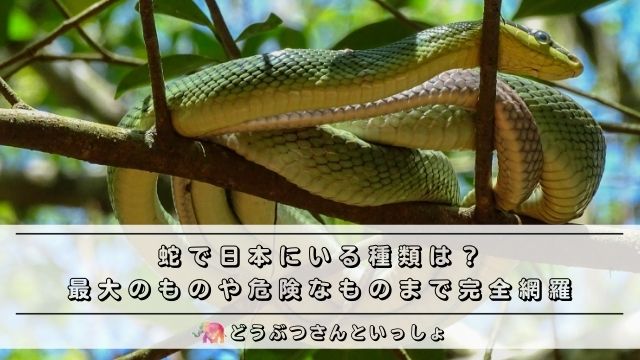
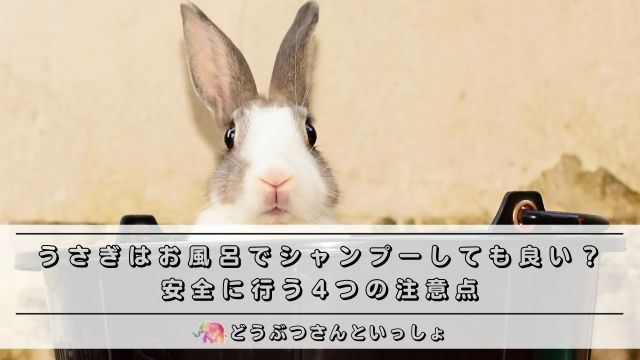

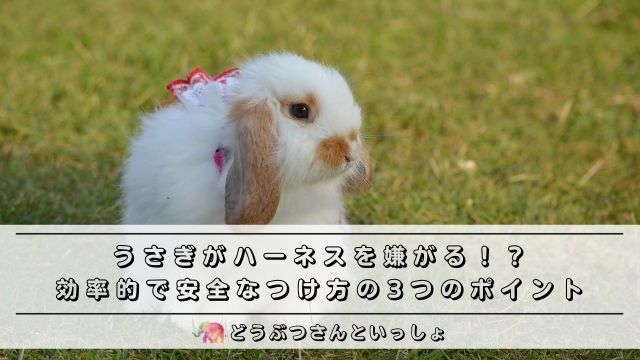
コメント